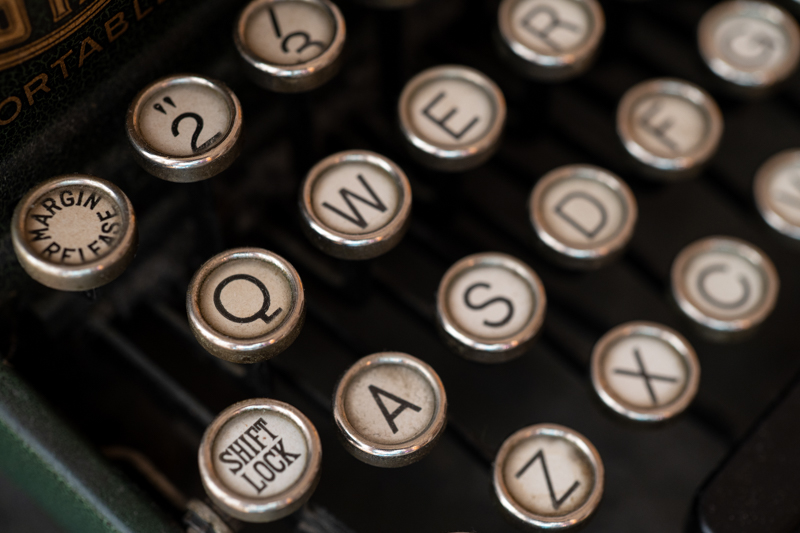赤城耕一の「アカギカメラ」
第123回:禁断の「オトナの自由研究」——ニコンZボディでミノルタ/ソニーAマウントレンズを使う
2025年8月5日 07:00
先日のことですが、ミラーレス機を最近購入し、写真をはじめたアマチュアカメラマンのビギナーの方に「なぜカメラメーカーが異なると交換レンズを共用できないのですか?」という質問をいただきました。
現在使用しているカメラから、異なるメーカーのカメラに乗り換えようと思えば、マウントも変わってしまうことが普通ですから、交換レンズもそれに合わせてすべて買い替えなければならないのは当然のことだと読者のみなさんは理解されていると思いますが、これを当たり前のこととする私たちはそれでいいのでしょうか。
そういえば、はるか昔の話ですが、筆者の父親も、筆者が駆け出しの時代、どのカメラメーカーを選ぶか悩んでいたときに、なぜ、異なるメーカー間で、レンズを共通使用できないのか、同じ疑問を持っていましたね。カメラのことなどなにも気にしないようでいて、この疑問はなかなかツボをついていたわけです。
筆者はこの質問を笑うことはできません。そうです、ビギナーさんの質問はたしかに的を射ているわけです。過去、ライカスクリューマウントとかプラクチカマウント、Kマウントなどユニバーサルマウントを目指したメーカーもありましたが、限られたメーカー間にとどまる格好になってしまいました。
いまは「Mマウント」や「マイクロフォーサーズマウント」、「Lマウント」がユニバーサルマウントの役目を果たしているところもありますが、これもすべてのメーカーが賛同しているわけではありません。
メーカー側としては1度カメラを購入したら、他のメーカーへの浮気は許しませんよ。という思惑もあるでしょう。メーカーとしては一眼レフユーザーからミラーレス機に買い替えていただくため純正のアダプターを用意するのは当然なのですが、一方で他メーカーのマウントの異なるレンズの面倒はみたくないわけであります。
交換レンズはカメラボディよりもはるかに利益率が高いそうですから、カメラメーカーとしては自分のところだけにお客さまを囲い込みたくなるのは当たり前ですね。
先のビギナーさんには「原則として、異なるメーカーのカメラとレンズは互換性はない」と答えるしかなかったわけですが、方法がないわけではありません。いまはとくにサードパーティから膨大なマウントアダプターが用意されていて、マウントのかたちだけでなく、電気的にも異なるメーカー間を繋ぐ試みが常に研究されているようです。
「電子マウントアダプター」と呼ばれるこれらによってAE・AFが使用できるのなら、異なるメーカーのレンズでも、純正レンズと同じ感覚で使用することができますからストレスが軽減され、先のビギナーさんの疑問にも応えることができるのですが、ただ、手放しでオススメすることはできません。
AFの合焦の精度とか挙動、機能的な制限などに加えて、マウントアダプターを使用した上での事故が起こることも皆無ではなく、これらはすべて自己責任になるわけで、このことをビギナーさんにご理解いただくのは少々ホネが折れますね。
電子マウントアダプターの種類が多いのは、ソニーα(Eマウント)シリーズ用のようです。これはミラーレス機の黎明期からαが頑張っていたからでありましょう。
αのすごいのはモーター非内蔵のAマウントレンズをEマウントに変換し、さらにAE・AF動作を可能にした純正電子アダプター「LA-EA5」を用意したことで、これはいまだにニコンも成し遂げていない快挙ともいえ、実用面においても感動的な動作をするマウントアダプターです。「LA-EA5」を使用してのAマウントレンズの動作感については本連載でもすでに報告しています。
今回は焦点工房からお借りした、EマウントレンズをZマウントレンズでAF動作するアダプター「Megadap ETZ21 Pro+」と、「LA-EA5」を2重に連結して、モーター非内蔵のAマウントレンズをニコンZでAFによる撮影ができないかを試みてみることにしました。
手持ちのEマウントレンズが少ないという理由もあるのですが、Aマウントのモーター非内蔵レンズの動作を見たかったという興味からであります。使用カメラはニコンZ5IIを用いています。良い子は真似してはいけない禁断の「オトナの夏休みの自由研究」というわけであります。
まったく個人的な話でいえば、筆者は、ミノルタやソニーのAマウントレンズの味わいがどうのという話にはほとんど興味がなく、異なるもの同士を結びつけることのできる絆というか、“連結の知恵”に強い興味があるわけです。
ニコンはレンズ内にAF駆動モーターを内蔵しないニッコールSやDタイプレンズをニコンZボディにおいて、AF動作させることのできる電子アダプターをいまだに用意していません。
この理由は先に述べたようにニコン独自の厳しい基準によるAF精度の維持や、これにかかるコストの問題もあると考えられますが、モーター非内蔵のAマウントレンズをニコンZに装着し、AF撮影をすることができたら痛快だし、もし実用的に使うことができれば儲けものじゃないかと考えるわけです。とくにミノルタ時代のAマウントレンズは中古市場では冗談ではないかと思えるくらいの価格がつけられていたりします。
ニコンユーザーのみなさんは真面目な方が多いので、一眼レフ時代はサードパーティのレンズやアクセサリーを自身のニコンカメラボディに装着することを嫌う方も少なからずいらしたのですが、ミラーレス時代を迎えてからは、少し事情が変わってきたように思います。
ニコンZのフランジバックの短さや、センサー前の極薄カバーガラスの特性を利用し、マウントアダプターを使用することで他社メーカーのレンズやオールドレンズを使用するユーザーも増えてきたように見受けられるのです。これはミラーレス後発の優位性というものでしょう。
異なるカメラメーカーのカメラやレンズを電子アダプターで繋ぐのは、電子信号の解析など、かなり高度な技術が必要なることは素人にも想像できることです。
筆者はこうした技術的知識とは1番遠いところにいるので、なぜそんなことが可能になるのか、1ミリも理解することはできません。
そこで、知人の電気に詳しいエンジニアに、筆者にもわかるように電子マウントアダプターの仕組みについて、簡単に解説してくれと頼んだら、彼は呆れるように私をみて、「早い話が、カメラを騙す、いや勘違いさせて動作させているんじゃないのかな」といっていました。
今回の例でいえば、「Megadap ETZ21 Pro+」と「LA-EA5」を2重連結させ、Aマウントレンズを使うと、Zボディはニッコールが装着されているのだと思い込み、AFを動作させてようと頑張るようなのです。おー! なるほどそうなのか。もちろん機能的な面では完全なウラはとれていませんけどAFは動作するのです。
使用した印象、結論を書いてしまいますけど、AF速度については不満を感じませんでした。Z5IIになって、積極的に使うようになったオートエリアAFとかAF-Aモードも純正Zレンズ並みにAマウントレンズで使用することができます。正確かどうかは不明ですが、各種撮影モードも機能し、被写体認識、顔認識や瞳認識も反応します。ボディ内の手ブレ補正も機能するようです。
測定器を使用するなどしてAFをはじめとする各種機能の精度を検証したわけはありませんが、実用上は十分であることがわかりました。
ただ、1つだけ、問題がありました。
どういうわけでしょうか、連写をするとAE時の露出が安定せず、ブラケッティングするようにバラついてしまうことがあるようです。
この現象は個体差かもしれず、常にこの現象が出現するわけでもないのではっきりと申し上げにくいのですが、使用した限りでは、コマ速を高速に設定にするほど、現象が出現する確率が上がるようなので、対処としてコマ速度を遅くした連写にするか、単写設定、あるいはマニュアル露出に設定にすれば防ぐことができるようです。
この現象を大きな問題とするか、しょせん反則技の遊びなのだから仕方ない、実用的には有効なのだから諦めるという考え方もあります。人それぞれの価値観の違いとなりますが、筆者は実用面を重視することにしました。お遊びだと考えれば、目くじらを立てる必要はないと考えています。
撮影をやりなおせる条件では、結果が悪ければ撮影をやり直せばいいことですし、なんとしてもここはイッパツで決めねばならないという条件では、マニュアル露出で撮影すれば済むことだからです。言うまでもなく大事な撮影にはこうしたお遊びをしてはいけません。
とはいえ、ここだけの話、筆者は先日のアサインメントの撮影で、今回のAマウントレンズとニコンZ5IIの組み合わせで使用してみたのですが、出来上がりはなんら問題にはなりませんでした。でもね、念のため繰り返しますが、良い子にはおすすめしないことを強調しておきます。
MINOLTA AF 20mm F2.8
ソニー時代になっても同じスペックのレンズの設計変更はないままでしたから、もともと優秀なレンズだったのです。
MINOLTA AF 24mm F2.8
コンパクトな24mmレンズで性能も優秀です。単焦点の余裕みたいなものも感じられます。Z50IIにつけて35mm相当画角で使いたくなります。
MINOLTA AF ZOOM 35-70mm F4
ミノルタα-7000時代(1985年)の標準ズームレンズ。とてもコンパクト。鏡筒が最も短くなる位置はテレ端の位置。ゴム部分が加水分解して悲しい姿になりました。
SONY 50mm F1.4
伝統のガウスタイプの50mm F1.4です。これはミノルタ時代から変わらずですね。モーターは非内蔵です。個人的に好きなレンズであります。
MINOLTA AF MACRO 50mm F2.8
ミノルタAマウントの初期の標準マクロレンズです。非常に不人気で、廉価です。1度呑みに行くのを我慢すれば購入することができます。デザインはものすごくカッコ悪く、鏡筒もツルツルです。
SONY 85mm F2.8 SAM
今回使用したAマウントレンズでは唯一、レンズ内にAFモーターが内蔵されています。音もなくスッと合焦します。鏡胴もマウントもプラスチッキーでものすごくお安い作り込みです。レンズ構成は4群5枚ですが写りは素晴らしかったりします。質量は175g。至近距離では実効F値が表示されますが、これは純正ニッコールレンズと同じです。
MINOLTA AF APO TELE ZOOM 100-300mm F4.5-5.6
小口径の望遠ズームレンズです。コンパクトで携行性は優れます。今回の試用では少し線の太い描写という印象を持ちました。実用性は十分です。大ボケ状態からAFを起動すると合焦に多少の時間を要しますので、使用にあたってはコツが必要です。
【2025年8月5日】初出時に「Megadap ETZ21 Pro」と記載していましたが、正しくは「「Megadap ETZ21 Pro+」になります。お詫びして訂正いたします。