切り貼りデジカメ実験室
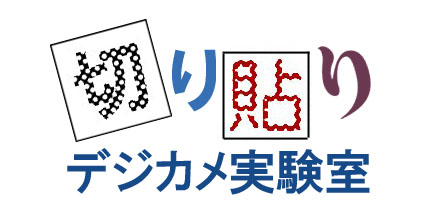
オリンパスで「オリンピアゾナー」を試す
レンズフードも自作してみた
2015年3月18日 10:00
1936年のベルリンオリンピック用ゾナーが現代に蘇る
今回紹介する「Carl Zeiss Jena 180mm f2.8」は、あこがれのレンズが「おっ」と思うような安い値段で売っていたので、つい購入してしまったものだ。通称「オリンピアゾナー」と呼ばれるこのレンズは、1936年開催のベルリンオリンピック用に、ヒットラーの命を受けたカール・ツァイスが、世界に冠たる光学メーカーの威信を賭けて開発したと言われている。
現在でも焦点距離200mm前後でF2.8の大口径望遠レンズは、スポーツやポートレート撮影用の定番とされているが、その元祖と言えるのがこのCarl Zeiss Jena 180mm f2.8なのである。
実際のベルリンオリンピックでは、同じくカール・ツァイスの新鋭カメラ「CONTAX II」に装着され記録写真が撮られた他、ムービーカメラに装着されレニ・リーフェンシュタールが記録映画「オリンピア」を撮ったことでも知られている。レニ・リーフェンシュタールは女優から映画監督に転身し、ヒットラーの寵愛を受け「オリンピア」や「意志の勝利」などナチス・ドイツのプロパガンダ映画を制作した。そのドイツも敗戦後は東西に分割され、それと共にカール・ツァイスも東西に分割されてしまった。
ぼくが買ったCarl Zeiss Jena 180mm f2.8はエクサクタマウント仕様で、東ドイツのCarl Zeiss Jenaから1950年代に発売されたタイプだ。基本的な光学系を初代から引き継ぎ、単層コーティングを施した改良品で、鏡筒デザインも一新され、各種一眼レフ用交換マウントが用意されていた。
ところがぼくが買ったレンズは経年変化でヘリコイドグリスが固まっていて、ピントリングが非常に重く、そのうち殆ど動かなくなってしまった。そこで修理を依頼することにしたのだが、やっと引き受けてくれる業者を見つけたものの、買った値段より高い見積もりを出され断念してしまった。
と言うわけでしばらくお蔵入りになっていたのだが、あるときふと思い付いて、画材店で購入した溶剤「ソルベント」を、ヘリコイドの隙間に垂らしてみたのである。ソルベントはペーパーセメント用の溶剤で、ぼくは自分の作品「フォトモ」の製作時に余分な接着剤を溶かすのに使っている。だからといってグリスも溶かせるとは限らないが、揮発性が高いので効果は無くともレンズへのダメージは無いはずだ。
と思って試してみたのだが、その結果は良好で、グリスが元の柔らかさを取り戻しピントリングが回るようになったのである。この効果は一時的なものではなく、半年以上経った今でもグリスは固まらずスムーズにピント操作ができているから、修理としては成功である。
そうなると、あらためて最新鋭のデジタルカメラに装着しその写りを試したくなる。ついでに、最新鋭のデジタルカメラ専用レンズと撮り比べもしたくなる。そこで今回は、オリンパスから発売された「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO」をお借りし、両者を「OLYMPUS OM-D E-M1」に装着してみることにした。
M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F2.8 PROはライカ判換算80-300mm相当の大口径望遠ズームで、オリンピアゾナーのコンセプトを継承したデジタルカメラ時代の末裔だと言える。さらにM.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F2.8 PROには専用の1.4倍テレコンバーター「MC-14」が用意されていて、これを装着すると56-210mm F4(ライカ判換算112-420mm相当)のスペックとなる。
対してCarl Zeiss Jena 180mm f2.8をE-M1に装着すると画角はライカ判換算360mm相当となり、このレンズの潜在能力がさらに引き出されることになる。またオリンパス製1.4倍テレコンバーターMC-14を装着して、252mm F4(ライカ判換算504mm相当)の超望遠レンズとして(もし画質が劣化しなければ)使うことができる。
ところでM.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F2.8 PROには、ワンタッチで引き出し可能な非常に素晴らしいレンズフードが付属している。しかし中古で買ったCarl Zeiss Jena 180mm f2.8にはフードが欠品していた。古いレンズのフードだけ探すのはほぼ絶望的だが、単層コーティングのレンズは有害光をカットするフードが必需品である。そこで以前製作したフードの発展形として、100円ショップで揃えた材料を元に、金属製で革張りのレンズフードを製作してみたので、その過程もご覧頂ければと思う。
―注意―- この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はデジカメWatch編集部、糸崎公朗および、メーカー、購入店もその責を負いません。
- デジカメWatch編集部および糸崎公朗は、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。
ソルベントについて(2017/06/16追記)
記事掲載後に、読者から、古いレンズに固着したグリスを柔らかくするため、レンズを分解せず隙間からソルベントを垂らす方法は危険ではないか? というご指摘をいただきました。この方法は、あくまで私の経験と勘に基づくもので、確実な化学的根拠に基づくものではありませんので、真似される方は自己責任において、ご判断いただければと思います。私の判断についてあらためてお答えしますと、本文中は確かに説明不足でしたが、私が使用した「ミツワ ペーパーセメント ソルベント」は本来、ペーパーセメントの溶剤として販売されているものです。このソルベントは、私も作品製作や工作用に長年使用しておりますが、特徴としましてはシンナーなど他の溶剤と比べて揮発性が極めて高いことと、溶剤としての力が弱い点が挙げられます。そこでもしこの方法が失敗しても、ソルベントの成分が揮発して、ダメージは最小限に抑えられると判断した次第です。
実際に私のオリンピアゾナーは、ソルベントを垂らした結果、グリスが柔らかくなりヘリコイドがスムーズに回るようになりました。記事執筆から2年あまり経った現時点で確認しましたが、当時よりヘリコイドがちょっと硬くなった気もしますが、以前のようにほとんど固着して回らない、ということはありません。また、グリスに溶けたソルベントが揮発して、内部のレンズに付着しているような現象も確認できません。
逆に言えば、揮発性が低く、溶剤としての力が強い、塗装用シンナーなどで同様のことを試されるのは、極めて危険だと思われます。KURE 5-56など浸透潤滑剤を注入することも、絶対にやってはならないと私は思います。プラスティック製の現代的なレンズについては、製造から日の浅いレンズはグリスの固着は考えられず、この方法を試す可能性はあまり感じられません。
しかしズームレンズについては、複雑なカム構造がありますから、ソルベントを垂らすという方法が悪影響を与える可能性もあります。また、複雑な自動絞り機構を持った、一眼レフ用レンズも同様の心配があります。記事中のオリンピアゾナーは、シンプルなプリセット絞り機構であり、だからこそ内部構造が単純で、私もこの方法を試したのです。
以上はあくまで私の経験とそれに基づいた見解に過ぎませんが、これを参考に、みなさんには自己責任で判断していただければと思います。
テスト撮影
カメラを三脚に固定し、レンズを交換しながら比較撮影を行った。各レンズとも、露出値を一定に保ちながら絞りを開放から1段ずつ絞って撮影している。ピントはMFで、画面中心部に合わせている。
- 作例のサムネイルをクリックすると、リサイズなし・補正なしの撮影画像をダウンロード後、800×600ピクセル前後の縮小画像を表示します。その後、クリックした箇所をピクセル等倍で表示します。
Carl Zeiss Jena 180mm f2.8(ライカ判換算360mm相当)
まず驚くのが、絞り開放2.8でのレンズフードの有無での描写の違いだ。フード無しでは全体的にフレアがかってコントラストが落ちていて、ピントは画面中心部に芯があるものの全体にぼやけている。
ところがフードを装着すると、コントラストが高くなると共にピントも格段にシャープになる。コーティング技術が未発達な時代のレンズなので、斜めから入射する光の悪影響がそれだけ大きいのだろう。
開放から絞るごとにコントラストとシャープさは向上し、F4~F16までは画面全体にわたってシャープな画像が得られる。しかしF22で回折現象の影響が大きく現れ、全体にピントが悪くなる。
色味は、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROに較べてアンバーに偏っている。
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO + MC-14(合成焦点距離180mm:ライカ判換算360mm相当)
Carl Zeiss Jena 180mm f2.8との比較のため、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROにMC-14を装着し、合成焦点距離180mmに固定しテスト撮影を行った。
ズームリングに180mmの指標はないが、E-M1のファインダーに焦点距離の表示が出るので便利だ。画角はCarl Zeiss Jena 180mm f2.8の方が少し狭く、どちらかの公称値がずれているのだろう。なお、このレンズの詳細なテストは 礒村浩一さんの交換レンズレビューをご覧いただきたい。
さて画質を比較すると、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO + MC-14画質は開放からシャープでコントラストが高く、あらためて驚いてしまう。さすが、オリンパスが誇る最新の高級ズームだけのことはある。しかしCarl Zeiss Jena 180mm f2.8は開発年や経年劣化を考慮すると、かなり頑張っていると言えるだろう。
Carl Zeiss Jena 180mm f2.8 + MC-14(合成焦点距離252mm / ライカ判換算504mm相当)
Carl Zeiss Jena 180mm f2.8にMC-14を装着してみたのだが、これがなかなかに高画質で驚いてしまった。テレコンを装着しないCarl Zeiss Jena 180mm f2.8と比較して、ほとんど画質の劣化がないように思える。
Carl Zeiss Jena 180mm f2.8の発売当初、このようなリアコンバージョンレンズはなかったはずで、実験としてはなかなか面白いと言える。
ライカ判換算504mm相当の撮影が可能になる。
実写作品とカメラの使用感
総じてE-M1はよくできたカメラで、78年前に設計されたCarl Zeiss Jena 180mm f2.8の潜在能力を、十二分に発揮することができる。もちろん、最新のM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROを装着すれば、それに相応しい機能を発揮できる。その意味で、システムカメラとして非常に柔軟性が高いと言える。
JPEGの画質設定は、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROとの比較を考慮して、シャープ+2、アンバー-2、に設定し、これをmyモード登録し、モードダイヤルの「iAUTO」で呼び出せるよう割り当てた。しかし、ぼくとしてはE-M1のモードダイヤル配列は疑問で、そもそもプロ用を謳うカメラに不要と思えるような項目が多すぎると思うのだ。
Carl Zeiss Jena 180mm f2.8(ライカ判換算360mm相当)
Carl Zeiss Jena 180mm f2.8は1,440gと重量級のレンズだ。第二次世界大戦前にこのレンズが開発された当時は、内面反射を防止するコーティング技術が確立されてなかった。そのためこのレンズをはじめとするゾナータイプは内面反射を押さえるため、分厚く曲率の高いレンズを数枚貼り合わせた構造をしている。なので重量もアップするわけだが、その重みが高性能の証でもあったのだ。
そんなCarl Zeiss Jena 180mm f2.8をE-M1に装着すると、EVFの倍率が大きく画素数も多いので、ピント合わせはし易い。ぼくはFn1ボタンを「ピント拡大」に割り当て「シャッター半押しで全画面表示に戻る」に設定した。今回の撮影は全てF5.6に固定して撮影したが、絞ってもEVFなら視野は明るく表示される。
また古いレンズでも手ブレ補正機能を使えるのが、E-M1をはじめとするオリンパスのマイクロフォーサーズカメラの利点だ。焦点距離は手動で180mm(テレコン使用時は250mm)にセットできる。お陰で安定したファインダー像を見ながら、ねっとりとした感触の精密なピント操作を楽しむことができる。
下の作品写真は、新宿界隈で撮影したものだ。はじめはビル街に漠然とレンズを向けていたが、そのうち窓の反射が面白くなって、その歪んだ像を撮り集めてみた。
Carl Zeiss Jena 180mm f2.8 + MC-14(合成焦点距離252mm / ライカ判換算504mm相当)
このレンズの組み合わせはメーカーとしては想定外だが、純正品の組みあわせに劣らず高性能を発揮するから面白い。
手ブレ補正機構のレンズ焦点距離は、手動で250mmに入力し直す必要がある。絞りは1段暗くなるので、すべてF8に固定して撮影した。
撮影は藤沢市の境川付近で行った。500mm相当と言えばかなりの望遠に思えるが、野鳥は小さい上に思うように近づけず、なかなかクローズアップできない。それでもカワウ、アオサギ、コサギ、イソシギ、ハクセキレイ、ムクドリと、目に付いた鳥を撮影した。
街中の野生動物は背景との関係性を表現するのがキモだと自分は思っているのだが、鳥は思うような位置に止まってくれず、自分も思うような場所に移動できず、なかなか難しい。
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO(ライカ判換算80~300mm相当)
使用感としてまず驚くのが、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROの軽さだ。880g(三脚座含む)で、これでライカ判換算80-300mm相当でF2.8のスペックがあるから驚きだ。まさに、撮像素子サイズが小さめのマイクロフォーサーズの利点が発揮された、優れて現代的なレンズだと言えるだろう。E-M1との組み合わせではAFも早く、まさに片手で気軽に望遠撮影ができてしまう。
と言うわけでゲリラ豪雨に見舞われた際、ふと思い立って傘を片手に300mm相当の望遠端で、銀座の街をスナップしてみた。オリンパス自慢の防塵防滴機能効果を、確認してみたくなったのである。その結果、望遠ならではの圧縮効果と浅い被写界深度によって、雨粒が印象的に描写できた。
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO + MC-14(合成焦点距離56-210mm相当:ライカ判換算112-420mm相当)
テレコンバーターのMC-14は小さくて薄いレンズで、装着したことを全く気にせず、焦点距離を1.4倍にスペックアップした撮影が楽しめる。絞りは1段暗くなるが、日中の撮影であれば特に不便は感じない。純正の組み合わせだけにAFは高速で作動し、画質の劣化も殆ど確認できない。
藤沢市内で撮影したが、この日はタイワンリスとコゲラを見つけた。タイワンリスは以前住んでいた国分寺市にはいなかった動物で、自分にとっては珍しい。コゲラはキツツキの一種で「コココッ」と木をつつく音でその存在をキャッチすることができる。
望遠レンズの難しさについて
連載で取りあげた、「ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6」は、画角120度の超超広角レンズであるにもかかわらず、我ながら上手く使いこなせるようになったという感触がある。
しかし今回使用した、300-500mmクラスの望遠撮影だと、なかなかそうも行かないと痛感してしまった。
そもそもぼくは中学生時代から近眼で、つまり遠くのものを見る習慣が殆ど無いのである。対して近くの虫などはよく観察するし、路上を歩きながら広い視界を見渡して「良い場所だなぁ」と感慨に耽ることもよくある。
そんな自分にとって、超超広角レンズの癖のあるパースペクティブに、自分の視点をチューニングして使いこなすことは、何とか可能だったのである。
ところが望遠レンズの場合、ファインダーを覗いただけで、正直何をどうして良いかわからなくなってしまうのだ。
「わからない」の1つに望遠ならではのパースペクティブの特性があるだろう。レンズが描くパースペクティブは、レンズの焦点距離(画角)ごとに特性が異なり、これを理屈でと言うより身体的に理解するのが、使いこなしの1つではないかと思うのだ。
いや、無理して自分の性に合わない望遠レンズを使わなくても良いだろう、と言う意見もあるかと思う。オリンピアゾナーも骨董品として愛でていれば、それで良いのかも知れない。しかし何かの機会にかこつけて(ぼくの場合はこの連載)、自分の慣れない分野にチャレンジすることで表現の幅は広がるのだ。
アメリカの写真家、リー・フリードランダーは「それまでアメリカの風景をフリードランダーのようなやり方で表象したアーティストは存在しなかった」と評されていて、ぼくはそんな言葉にしびれてしまう。
つまりもしその人が、超望遠レンズの特殊なパースペクティブを自らのものとしたならば、これまでだれもしなかったようなやり方で、「東京」や「日本」の風景を撮ることができるかもしれない、そんなふうにも考えられるのだ。
