切り貼りデジカメ実験室
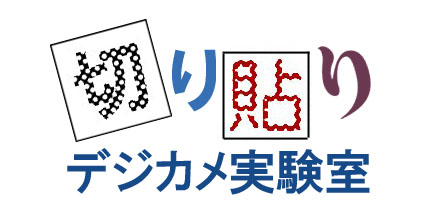
ULTRA WIDE-HELIAR 12mm専用「開閉式バリア付きフード」を作る!
“遠近法的に正しく視覚心理的に間違っている”?
Reported by 糸崎公朗(2015/1/5 12:00)
レンズキャップ紛失からひらめいたアイデアを実現
「ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical」(以下ULTRA WIDE-HELIAR 12mm)は、この連載でも2011年11月と2012年12月に採り上げたが、私はその後、このレンズ専用キャップを失くしてしまったのである。
そこで今回は、このレンズのために「開閉式レンズバリア」を製作することにした。私はこの連載でたびたび交換レンズにバリアを内蔵するプランを提示しているが、その広角バージョンである。
さて、私が尊敬する写真家の田村彰英先生が2014年4月に出版された「田村彰英 変遷1995-2012」という写真集には、1900年にドイツのゴルツ社によって開発された伝説的超広角レンズ「Hypergon」(ハイパーゴン)で撮影された写真が収録されている。
ハイパーゴンは8×10の大判フィルムカメラに装着すると、画角135度もの超超広角撮影が可能で、しかも魚眼レンズとは異なり直線が歪まずまっすぐに写る。私は田村先生がこのレンズで撮影した、強烈なパースペクティブを持ったモノクロ写真に思わず引き込まれてしまった。
と同時に、自分が同等の画角を持つ現代の超超広角レンズULTRA WIDE-HELIAR 12mmを所有していたのを思い出したのだった。
これはハイパーゴンの開発からちょうど100年後の2000年にコシナから発売されたLマウントのレンズで、画角はハイパーゴンに少し及ばないながらも120度を誇る(現在は光学系をそのままに鏡筒を一新したMマウント仕様の「ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical II」 が発売されている)。
私はこのULTRA WIDE-HELIAR 12mmをフィルムカメラ「ベッサL」と共に2003年に購入した。当時の私は大阪HEPFIVEでの個展を控え、このために大型作品「フォトモ・戎橋」の製作に燃えていたのだが、道頓堀川の川面を継ぎ目なくワンショットで撮影するためこのレンズがどうしても必要だったのだ。
しかし画角121度の超超広角レンズはあまりに特殊でこの用途以外に使うことができず、フィルム1本を通しただけでずっと死蔵していた。
このレンズを私が再び使い出したのは、ライカM互換マウントを採用した「RICOH GXR A12 MOUNT」を入手してからだが、APS-Cのデジカメに装着すると超広角18mm相当の比較的使いやすい画角になるのだ。
しかし田村彰英先生がハイパーゴンで撮影した作品を見て、ULTRA WIDE-HELIAR 12mmをライカ判フルサイズデジカメに装着し、このレンズ本来の画角121度で撮影してみたくなったのだ。そこで今回はレンズの改造記事にかこつけてソニー「α7R」をメーカーさんからお借りしたのである。
ところが私は、このレンズに付属の専用キャップをうっかり失くしてしまったのだ。というわけで、そこで今回はULTRA WIDE-HELIAR 12mmのために開閉式レンズバリアを内蔵したフードを製作することにした。
―注意―- この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はデジカメWatch編集部、糸崎公朗および、メーカー、購入店もその責を負いません。
- デジカメWatch編集部および糸崎公朗は、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。
テスト撮影
「開閉式バリア付きフード」が完成したところで、レンズ描写を確認するためのテストを行った。被写体は、被写界深度や歪曲収差などがいちどにチェックできる金網越しの風景を選んだ。
カメラを三脚にセットし、ピントは無限遠に固定、マニュアルモードで一定の露出値を保ちながら、絞りを一段ずつ変えている。
テスト結果だが、絞り開放から画面中心付近は実にシャープで驚いてしまう。画面周辺部は像が崩れるが、絞るごとに改善する。しかしF11では回折現象のため僅かに中心部のシャープさが失われ、F22ではかえって全体がぼやけてしまう。
手前の金網からカメラまでの距離は約1.5mだが、絞り開放から無限遠まで被写界深度の範囲内に収まっている。歪曲収差はほぼ皆無で、直線の被写体が直線として写っている。逆光の条件だが、軽微なフレアーが掛かるだけで、ゴーストは発生していない。周辺光量の低下は絞り開放から目立ち、絞っても改善されない。
フィルムカメラが主流の時代に発売されたレンズだが、α7Rとの組み合わせでも十分高性能が発揮できると言えるだろう。また参考までに、このレンズの驚異的な画角の広さを知ってもらうため同じ位置からiPhone 5で撮影した画像(画角33mm相当)も最後に並べてみた。
- 作例のサムネイルをクリックすると、リサイズなし・補正なしの撮影画像をダウンロード後、800×600ピクセル前後の縮小画像を表示します。その後、クリックした箇所をピクセル等倍で表示します。
魚眼レンズとの比較
次に、これは私の興味からなのだが、同じく広い画角を持つ「魚眼レンズ」との比較撮影を行ってみた。使用したのはAマウントのソニー「16mm F2.8 Fisheye」でマウントアダプター「LA-EA4」を介してα7Rに装着した。ピントはマニュアルで無限遠に合わせ、絞りはF5.6で、同一位置から撮影している。
結果を見ると、魚眼レンズは直線が湾曲して写っているのがよくわかる。この描写はいかにも不自然に思えるが「近くの物は大きく描写し、遠くに行くに従って小さく描写する」という遠近法に忠実なのは、実は魚眼レンズの方なのである。
なぜならこのテスト撮影は金網の前から約1.5mの距離にカメラを設置しているが、画面の隅に写る金網はカメラからさらに遠く離れているのだ。
そう考え見るとULTRA WIDE-HELIAR 12mmで撮った写真は、近くの金網も遠くの金網も同じ大きさに写っていて、文字通りの遠近法に反している。
画角121度のULTRA WIDE-HELIAR 12mmについて計算して考えると、実はこのレンズは画面中心部こそ“焦点距離12mm”だが、画面隅は“焦点距離24mm”に伸びている。おかしな話に思えるが、歪曲収差が抑えられた広角レンズは、画面中心より周辺部の方が望遠になっていて、ものがより大きく写るのだ。
そもそもレンズが描く遠近法は、ルネッサンス期に確立された絵画の遠近画法に基づいている。しかし人間の視覚像が球面の網膜に映されるのに対し、絵画も写真も平面で、しかも人は広い視界を1度に認識せず、部分的な視界を記憶でつなぎ合わせている。
このように人間の視覚心理と絵画(写真)の原理はさまざまな点で異なり、その矛盾が画角の広いレンズになるほど顕著になる。実際、超広角レンズに相当する画角で描かれたレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」は、遠近法の不自然さを意図的に修正して描かれている! のだ。
つまり画角121度のULTRA WIDE-HELIAR 12mmの描写は、言ってみれば「遠近法的に正しく視覚心理的に間違っている」のであり、この特徴をよく理解するのが使いこなしのコツと言えるだろう。
実写作品とカメラの使用感
本来、ULTRA WIDE-HELIAR 12mmはLマウントのフィルムカメラに装着し、専用の光学ファインダーを覗いて構図を決定する。しかしこのファインダーには歪曲収差があり、撮影された写真は異なっている。
しかし同レンズをα7Rに装着すると、ライブビューによって撮影する写真そのままの構図が確認できる。画角121度の強烈なパースペクティブを直接確認できるこの機能は、大変に有意義だと言える。α7Rそのものはライカ判フルサイズセンサーを搭載しながら実に小型軽量で、使い勝手も良好だ。
このレンズはMF仕様だが、テスト撮影で見たとおり被写界深度が深く、風景撮影においてはピント合わせ不要のパンフォーカスとして使用できる。あとは露出モードを絞り優先に設定すれば、シャッターを押すだけでサクサク軽快に撮影できる。
今回製作した「開閉式バリア付きフード」も我ながら非常に実用的で、キャップの紛失を心配せずに撮影に専念できる。
が、このレンズの画角121度が生み出すパースペクティブは尋常ではなく、とても気軽に撮影できるものではない。何しろファインダーを覗くと目の前の風景が遙かに遠のいて見え、自分のほぼ真横にあると思えるものまでが画面に写り込んでいる。
さらに直線がまっすぐ写りながらあらゆるものの角度が不自然に曲がり、肉眼で見える風景との激しいギャップにめまいがしてしまう。まさに「遠近法的に正しく視覚心理的に間違っている」というのがこのレンズの特徴なのだ。
とは言いながら、実は人間の視覚心理は一方では実にいい加減で順応性に富んでいる。つまり何度か撮影を試みるうちに、徐々にこのレンズの画角121度に目が馴染んでくるのである。そうなると、このレンズならではパースペクティブをどんな風に作画に利用しようかというアイデアも湧いてきて、撮影もだんだん楽しくなってくる。
というわけで今回の実写作品は、田村彰英先生のハイパーゴンによるモノクロ写真にあやかり、α7Rの画像設定をモノクロにして撮影してみた。先人の真似をすることでその凄さを理解することも、写真の勉強には必要なのである。
