切り貼りデジカメ実験室
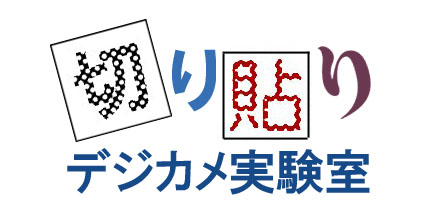
ポラロイドのプリンター内蔵デジカメで「フォトモ」を作る
(2013/2/5 00:38)
デジタル版ポラロイド写真から立体作品「フォトモ」をつくる
先月、本誌「デジカメアイテム丼」で水咲奈々さんによるプリンター内蔵デジカメ「Z2300」のリポートが掲載されていたのだが、ふとこれで「フォトモ」を作ってみようというアイデアが閃いた。
フォトモについては「Web写真界隈」のインタビュー記事でも紹介されているが、ぼくの代表作にして「切り貼り」的思考の原点となったシリーズだ。簡単に言えば、フォトモとは「写真プリントを切り抜き、立体的に再構成して制作する3D写真の一種」である。言い換えれば「写真を素材とした模型」であって、ぼくはこれをフォト(写真)+モデル(模型)の略語として「フォトモ」と命名したのだ。
フォトモを制作するには、プリントの素材が問題になる。ぼくがこの技法を始めたのはまだフィルム全盛の1990年代初頭だったが、それもあってフォトモの素材には銀塩のカラープリントを使用してきた。これが切ったり曲げたり貼ったりする工作素材としても最適なのだ。
しかしデジタルの時代になって、インクジェットプリントを試してみたのだが、意外なことにフォトモの素材としては適さないのだ。表面にインクを吹き付けるインクジェットプリントは、折り曲げた部分のインクが禿げたりして、非常に扱いにくい。
そこで気になるのがZ2300に採用された、ZINK Imaging社開発の「ZINKペーパー」の性質だ。調べてみると、感熱式の染料結晶が塗布された層を、ポリマーオーバーコート層で保護した構造らしい。店頭で試させてもらったところ、プリントを折り曲げた箇所が傷むことなく、表面も丈夫で工作の素材として適していることが確認できた。というわけで、さっそく編集部経由でZ2300をお借りして、ZINKペーパーによるフォトモ制作にチャレンジしてみた。
―注意―- この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はデジカメWatch編集部、糸崎公朗および、メーカー、購入店もその責を負いません。
- デジカメWatch編集部および糸崎公朗は、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。
カメラの確認と撮影の工夫
フォトモ制作編
フォトモ完成編
「フォトモ」と「写真」の関係について
ここのところ、この連載を通じて「反-反写真」のコンセプトのもと「写真」を追求してきたが、今回は原点回帰として、久しぶりに「フォトモ」を製作してみた。フォトモの手法は、実のところ「写真が撮れない」という自分の挫折から生み出されたもので、その意味ではまさに「反写真」なのである。
フォトモは立体作品であり、従って写真に付き物の「四角い画面」や「構図」と言った概念から解放されている。逆の見方をすれば、ぼくは四角い画面に構図を収めて写真を撮ることの意味がどうしても理解できず、その反動からフォトモの手法を見出したと言える。
恐らくそれは、写真の形式そのものがあまりに「自明」となっているため、それを対象化して分析的に捉えることができない事が原因ではないかと、最近は思っている。
写真に限らず、物事を分析的に捉えられなければ、それをコントロールして自分の表現を生み出すことはできない。対象物を分析的に捉えられなければ、その対象は「自明」というモヤモヤした塊でしかなく、原因不明の病人に対した医者のように、どうにも手の施しようがないのである。
ぼくにとっての「写真」とは、そのように取り付く島もないような対象物なのであり、だからフォトモの技法によって、突破口を見出そうとしたのかも知れない。
自分が見出した技法であるフォトモには先駆者が存在せず、それが何であるかの自明性も存在しない。従って、自ら分析的に捉えようとしなければ、フォトモは制作できない。フォトモには自明性がないからこそ、自ら分析的に手法を発展させることが可能であり、その中にぼくは「作る喜び」を見出したのだった。
ところがそのようにフォトモを作り続けて何年も経つと、どういうわけかだんだんと飽きがきてしまう。自分としてはフォトモで表現できることのあらゆるパターンを試そうとしたのだが、徐々にそれがやり尽くされてしまう。はじめは新鮮だったフォトモの手法が、自分の中でいつのまにか自明化してきたのかも知れない。
実のところどんな対象物も、それだけを見つめていると目の前から消えてしまう。なぜならあらゆる認識は、他のものとの比較において成立しているからだ。フォトモをはじめとするぼくの作品は「写真」の否定の上に成立しているが、だからこそ一方で「写真」ときちんと対峙する必要もあったのだろう。今回は久しぶりにフォトモを制作しながら、そんなことを考えてしまった。
