切り貼りデジカメ実験室
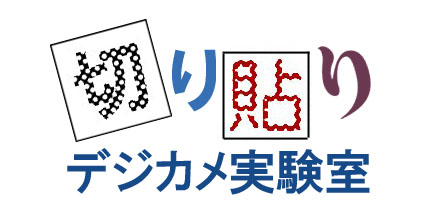
レンズを使わずに撮影する「レンズがない写真」
撮像素子に影を投影する“デジタルフォトグラム”
2016年6月24日 08:00
最初に「写ルンです」で試した「レンズのない写真」
「写真はレンズで決まる」とはかつてヤシカが発売していたCONTAXシステムのキャッチフレーズだが、「レンズがない写真」というものを考えた。
いや私が「レンズがない写真」を考えたのは、確か1991年だったと思うのだが、もう25年も前のことである。当時の私は、まだ写真を立体加工する「フォトモ」の表現を思い付く前で、美大を卒業した自分が何をなすべきか日々思い悩んでいたのだった。
そんなとき、ふと思い付いたのが、使い切りカメラ「写ルンです」のレンズとシャッターを切除し、フィルムに直接モノを置いて、撮影する技法だったのである。
まぁ、印画紙に直接モノを置いて露光する「フォトグラム」の技法は以前からあったのだが、フィルムにモノを置いて撮ったという話は聞いたことがない。
それで早速実行してみたのだが、光源はストロボのマニュアル発光で、部屋を真っ暗にして、フィルムの上にビーズとかクモの標本などを置いて、露光してみたのだった。
また、フィルムの上にラップを敷いて、その上にペットショップで買った透明の熱帯魚を乗せて、露光してみたりもした。
撮れた写真はそれなりに面白かったのだが、しかし当時の自分としては「この作品でアーティストになる」というビジョンがどうも持てなくて、ちょっと試しただけでお蔵入りになってしまったのだった。
――と、以上のことを20年余の歳月を経てとつぜん思い出したのだが、ともかくこの連載のために無い知恵を絞って、記憶の奥底から蘇らせたアイデアを、デジタルに応用してみようというのである。
デジタルで「レンズがない写真」を実行する
さてデジタル版「レンズがない写真」を実行したいのだが、最新のデジカメを使って撮像素子を汚したり傷つけても仕方がない。そこで型落ちのE-P1を使う事にした。
私のE-P1は以前にこの連載でも紹介したように、グリップを外して革張りしたスペシャルバージョンなのだが、さすがに古くなって出番がなくなっていた。
E-P1はミラーレスカメラのため、レンズを外すと撮像素子が剥き出しとなり、さらに独自の超音波駆動によるダストリダクションシステムを備え、この手の実験には最適なのである。
ところがあらためて確認してみると、レンズを外したE-P1は撮像素子が剥き出しだが、シャッターボタンを押した瞬間フォーカルプレーンシャッターが開閉動作するのである。
例えこのシャッターを除外したとしても、撮像素子の前面にはIRカットフィルターやローパスフィルターなどのガラス層があり「撮像素子に直接モノを置いて露光する」ことは原理的に不可能だとわかった。
そこで、かつてフィルムで行った実験を、完全にデジタルで再現することはあきらめて、レンズを外したマウントにガラスフィルターを乗せて、そこにモノを置いてともかく撮影することにした。
光源はストロボではなく、iPhone 6の内蔵LEDライトを使う事にしたが、点光源のため距離を置いて照射するとクッキリとした影が出るのである。
それで早速試しに撮影してみると、以前フィルムで行ったのとはまた違った表現になり、これはかなりイケそうだ。デジタルの場合は撮影結果がすぐわかるし、背面モニターを見ながら微調整もできるので、いろいろな“被写体”で実験してみたのである。
―注意―- 本記事はメーカーの想定する使い方とは異なります。糸崎公朗およびデジカメ Watch編集部がメーカーに断りなく企画した内容ですので、類似の行為を行う方は自己責任でお願いします。
- この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はデジカメ Watch編集部、糸崎公朗および、メーカー、購入店もその責を負いません。
- デジカメ Watch編集部および糸崎公朗は、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。
カメラとレンズの工夫
実写作品
今回はいつも以上にスゴイ写真が撮れてしまって、我ながら驚いている。
そもそも「写真」とは文字通りの意味としては「目で見たとおりの真実を写す」とされている。ところが、今回の撮影技法は「目に見えないもの」をデジカメの撮像素子に写すのである。
だから例えばガラス瓶を写すにしても、「目で見たとおりのガラス瓶」とは全く違う写り方をするので、事前にどんな写真になるか予想がつかないのだ。
しかし1つ分かったのは、不透明の被写体はぼやけたシルエットが写るだけで、あまり面白味がない、ということだ。
だから身の回りの透明なものをいろいろ探して、被写体としてみたのだが、前途のように何がどう写るのか事前には想像も付かないので、撮影としてはなかなか新鮮な体験ができた。
◇ ◇
100円ショップで買った、ガラス製ワイングラスを垂直に置いて撮ってみた。虹色に分解した光のハレーションが美しい。
同じワイングラスを横倒しに置いて撮ってみたところ、先ほどとは全く異なる表現になって驚いてしまった。まるで顕微鏡写真のような不思議な世界が写し出されている。
今度はワインの空き瓶を撮ってみたが、これも肉眼とは全く異なるディテールが写し出された。ガラスに不純物が混じっているせいなのだろうか?
ドリンク剤が入っていた、色付きのガラス瓶。瓶の位置や傾き方によって写り方が異なるので、ベストの写りになるよう調整した。
ジャムが入っていた空き瓶の底から撮ってみた。瓶底の外周に滑り止めのイボイボが並んでいるが、その光の屈折が不思議な模様を作りだしている。
100円ショップで、3色の透明プラスティックでできたフォークを買ってきて、それらを組み合わせて撮影。写真を撮ると言うよりも、抽象絵画を描く感覚で、被写体の位置や角度を調整してシャッターを切った。
上記と同様のフォークだが、撮影する部分を変えると写真の表情も驚くほど変化する。
こちらは同じく100円ショップで買った、透明な歯ブラシの柄の部分。実はブラシの部分を撮ろうと思って買ってみたのだが、実際に撮影すると柄の部分の方が面白く、しかもビニール袋に入ったままの方がなんだかわからない不思議な写真になったのである。
上記の歯ブラシが入っていた透明ビニールだけを撮ってみた。未知の惑星の表面のような、不思議な立体感がある。
急須に入っていた茶こしの金網だが、不透明の被写体も選び方を工夫すれば面白い写真が撮れる。網が歪んでいるため、画面に立体的な変化がもたらされている。
まとめ
25年前の私は、自分で撮った「レンズがない写真」の可能性に確信が持てなかったのだが、いまあらためてデジタルでこの技法を試すと、モニターで確認しながら撮影できる手軽さもあって、ずいぶん面白い。
何よりも表現に驚きがあり、これはちょっと本腰を入れて、自分の新しい表現として取り組んでみたいとあらためて思ってしまった。
先にも書いたように、今回の技法は印画紙にモノを置いて撮影するフォトグラムと基本的には同じであって、調べてみると写真術の発明者のひとり、イギリスのフォックス・タルボットが1830年代に早くもこの技法を試している。
以後は1910年代末にドイツ人クリスチャン・シャドが、1920年代初めにはフランス人マン・レイとハンガリーのモホリ=ナギが、フォトグラムの技法で作品を製作している。日本では画家の瑛九(えいきゅう)が1936年にフォトグラムによる作品集を出版している。
それ以外にもさまざまなアーティストがフォトグラムの技法による作品を製作しており、これをもってオリジナリティがあると言うことはできない。また、かつて私が試した「フィルムに直接モノを置く」フォトグラムも、調べれば誰かが先にやっている可能性も無いとは言えないだろう。
そもそも今回試した技法は、完全なフォトグラムではなく、被写体が撮像素子に密着せずに約2cm、つまりマイクロフォーサーズ規格のフランジバックの分だけ離れているのである。
しかも被写体に透明な物体を選んで、その光の屈折を写しているのだから、これは「レンズのない写真」と言うよりも、「レンズの形をしていないレンズによる写真」だと言えるかも知れない。
しかし表現というのは技法や理屈よりも結果が重要なのであって、ともかく今回はこれまで見たことがないような作品ができて、自分としては満足している。
いや、これまでの自分の表現とはまた違った作品を作って「糸崎はなにをやってるんだ」と多くの方々は思われるかも知れないが、私としては「この道一筋」のアーティストよりも、多様な表現に挑むアーティストにどうしても惹かれてしまうのである。
その意味で言えば、先に挙げたフォトグラムを制作したアーティスト、マン・レイ、モホリ=ナギ、瑛九らはいずれも絵を描いたり写真を撮ったり、多様な表現を行っているのである。
アーティストだけでなく、例えば今どきはカメラメーカーもカメラだけを作っているのではなく、オリンパスは内視鏡メーカーでもあるし、ニコンは半導体製造装置メーカーでもあるし、富士フイルムは医薬品も作っている。
そんな中、自分が写真家だからと言って「写真」だけ撮っていて良いのだろうか? と言うようなことをずっと考え続けてきて、そして自分のデビュー前のアイデアが、25年の歳月を経てようやく日の目を見ることができたのである。
