切り貼りデジカメ実験室
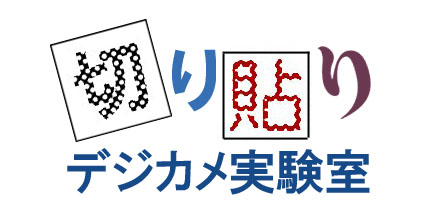
Macro Quinon 55mm F1.9のポテンシャルをOLYMPUS PEN-Fで引き出す
黎明期のマクロレンズが現代の技術で蘇る!
2016年7月1日 07:00
スペック偏重のスーパーマクロレンズを実用的にアレンジ
今回は「Macro Quinon(マクロクィノン)55mm F1.9」というレンズを取りあげたいのだが、このレンズはとにかく凄すぎて、だいぶ以前に中古で買ったにもかかわらず、ずっと使えないままでいたのである。
このMacro Quinon 55mm F1.9はドイツのSteinheil(シュタンハイル)社から1965年に発売された、初期のマクロレンズの1つである。
Macro Quinon 55mm F1.9の凄いところは、まずマクロレンズにもかかわらずF1.9と大口径である点だ。この明るさは同時期のマクロレンズとしてはスイス製「Macro Switar(マクロスウィター)50mm F1.8」に匹敵するが、Macro Switarは最大撮影倍率1/3倍止まりなのである。
ところがMacro Quinon 55mm F1.9は、最大撮影倍率が等倍を超える1.4倍を実現しているのである。
ちなみに同時期の国産マクロレンズの多くが口径比F3.5、最大撮影倍率1/2倍止まりなのである。また等倍を超えるマクロレンズは、現代に到るまでごく少数しか存在しない。それを考えるとMacro Quinon 55mm F1.9がどれだけ凄いかがわかるだろう。
ところがMacro Quinon 55mm F1.9はスペックだけが追求され、使い勝手はほとんど考慮されていないフシがある。まず、マウントは「エクサクタマウント」で、以前の記事でも紹介したが、エクサクタは左手仕様のドイツ製一眼レフで、使い勝手が非常に悪い。
1.4倍ものマクロ撮影ができるのは良いとして、その際のワーキングディスタンス(レンズ先端から被写体までの距離)が約4cmと非常に短いのである。重量は500gもあり、50mmクラスのマクロレンズとしては異例の重さである。
このレンズが発売された1965年頃は、ニコンやペンタックスなど日本製一眼レフが台頭してきており、エクサクタマウントは時代遅れになりつつあった。また、明るさと倍率を抑えた国産マクロレンズの方が結局のところ実用的で、Steinheilを初めとするヨーロッパの多くの光学メーカーは、撤退や廃業を余儀なくされたのである。
そのようにMacro Quinon 55mm F1.9は時代遅れの要素と、時代を先取りした要素を併せ持つ大変興味深いレンズで、私は9年前の2007年に、中古でけっこうな値段がしたにもかかわらず、無理をして買ってしまったのである。
ところが当時使っていたオリンパスE-300にマウントアダプターを介してMacro Quinon 55mm F1.9を装着してみたのだが、思った以上に使いこなしが難しいのである。まず、マクロ撮影ではブレを押さえるためにストロボ照明が必要なのだが、ここまでワーキングディスタンスが短いと、ストロボ照明に特殊な工夫が必要になる。
ところがどういうわけか、このレンズのフィルター径が52mmでも55mmでもない特殊規格で、レンズ先端にディフューザーなどを簡単に装着することができない。いや実は、この連載でたびたび紹介しているようなストロボディフューザーを仮止めして撮影してみたのだが、倍率を上げて撮影するとなぜかフレアが掛かってコントラストが落ちて写るのである。
そういう大変さがあって、せっかく買ったこのすごいレンズを、私はほとんど使えずにいたのである。しかし、この連載「切り貼りデジカメ実験室」では、これまでマクロ撮影についてのさまざまな工夫を試みてきており、そろそろMacro Quinon 55mm F1.9についての問題もクリアできそうな気になったのである。
そこで今回は、最新のテクノロジーによってMacro Quinon 55mm F1.9のポテンシャルをフルに引き出す試みをしたいと思う。
―注意―- 本記事はメーカーの想定する使い方とは異なります。糸崎公朗およびデジカメ Watch編集部がメーカーに断りなく企画した内容ですので、類似の行為を行う方は自己責任でお願いします。
- この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はデジカメ Watch編集部、糸崎公朗および、メーカー、購入店もその責を負いません。
- デジカメ Watch編集部および糸崎公朗は、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。
カメラとレンズの工夫
はじめに、今回取りあげるレンズMacro Quinon 55mm F1.9の紹介をしよう。私の持っているのはエクサクタマウントで、以前の連載でも紹介した「外部連動絞り」が作動するシャッターボタンをレンズ側に備えている。
Macro Quinon 55mm F1.9はその名の通りマクロレンズで、レンズ根元のピントリングを回すと鏡筒が繰り出し、撮影倍率1/2倍を超える1/1.4倍の撮影ができる。
さらにこのレンズにはカラクリがあって、レンズ先端にもう1つピントリングを装備し、これを回すとさらに鏡筒が繰り出し、1倍(等倍)を超える1.4倍もの撮影ができる。ちなみに1段目のピントリングを回しきらない限り、2段目のピントリングにはロックがかかって回らない仕組みになっている。それぞれのピントリングに撮影距離と倍率、そして露出倍数(レンズを繰り出すとF値が暗くなるのでその計算倍数)が表記されいる。
2段式ヘリコイドを内蔵するため、レンズそのものは奥に引っ込んでおり、鏡筒そのものが遮光フードの役を果たしている。しかし古いレンズのためコーティングが弱く、逆光には強くない。レンズ構成は戦後の一眼レフによく使われはじめた「ダブルガウス(4群6枚)」で、撮影倍率を上げても画質の劣化が少ないとされているタイプだ。
レンズを最大に繰り出した状態で、マウント側からレンズ内部を撮ってみた。外部連動絞りを作動させるためのロッドが延びているのが分かる。繊細かつ精密な機構で、同時代の日本製品を凌駕していたが、エクサクタマウント自体が時代遅れになっていたのである。また、現代のマクロレンズでは一般的な「フローティングフォーカス機構」もまだ装備されていない。
さて、今回はそんなMacro Quinon 55mm F1.9を、最新のデジタルカメラOLYMPUS PEN-Fに装着し、そのポテンシャルを引き出すことにしよう。
実は「OM-Dでエクサクタマウントの自動絞りを動かす」で製作した「自動絞りアダプター」を使用したかったのだが、安物のマウントアダプターをベースにしたためレンズ固定ピンが壊れてしまったのである。そこで今回は、焦点工房が扱っているKIPON製のエクサクタ→マイクロフォーサーズマウント変換アダプター「EXA-m4/3」を、無改造で使用することにした。レンズの絞りは固定で使う事になるが、モニターでピント確認できるPEN-Fで使う分には、実用上で不便を感じることは無い。
Macro Quinon 55mm F1.9を装着したところ。レンズが大きくてちょっとアンバランスだが、クラシックスタイルのPEN-Fとなかなか合っていると言える。
ピントリングを最大に繰り出したところだが、さらにアンバランスな特殊メカの出で立ちになる。この状態で1.4倍のマクロ撮影が可能になるが、マイクロフォーサーズ規格のPEN-Fに装着した場合はライカ判換算2.8倍相当になり、これがこの規格のデジカメの利点でもあるのだ。しかしこの状態のワーキングディスタンスは約4cmで、長く延びた鏡筒と相まって、ストロボの照明が難しい。しかもフィルター径が特殊サイズで、レンズ先端に自作アダプターを装着することも簡単ではないのである。
さて改造だが、まずこのレンズは条件によっては内面反射によるフレアが出るので、これを押さえるためのフレアカッターを装着する。このアイデアは以前に紹介した「コニカARマウントレンズとOM-Dでマクロ撮影を試す」の応用である。もちろん「ライカ判フルサイズ」のカメラに装着した場合ケラレが生じるが、マイクロフォーサーズ規格のカメラではその心配は無く、フレアの原因となる有害光を効果的にカットすることが見込まれる。
実はこのフレアカッター、この連載の「ジャンクカメラで作るレンズバリア内蔵キャップ」で紹介したものを、両面テープでレンズ先端内側に貼り付けているのである。なので赤いスイッチをスライドさせると、バリアがカチッと閉じてレンズを保護できる。ちなみに交換レンズ用の「バリア内蔵キャップ」は今でこそ一般化しているが、当時はまだ存在していなかったように思う。
次はストロボの改造だが、工程を省くためにこの連載の「『高倍率超マクロ』のストロボシステムを考える」で製作した改造ストロボを再利用する。改造としては、サンパックの小型ストロボ「PF20XD」から発光部(キセノン管)を摘出し、コードで延長している。
この連載の「驚異の“18倍マクロ撮影”に挑戦」では「マクロ用ライトボックス」を制作したが、今回はそれを応用したものを作ろうと思う。まずはAdobe Illustratorで図面を描き、それを元に部品の「型紙」を描いてプリントアウトする。
「マクロ用ライトボックス」の素材は、前回と同様100円ショップで購入したポリプロピレン製ファイルを使用する。これに上記の型紙を、スプレー糊を使い貼り付ける。
型紙を元にファイルをカットして折り目を付けると、ご覧のような3つのパーツができ上がる。
各パーツの裏側には、スプレー糊でアルミホイルを貼り付けた。
さらにストロボの発光部に当たる部分のために、ディフューザー(散光板)を製作する。素材は同じく100円ショップで買った、透明のポリプロピレン製ファイルを使用した。
全てのパーツを組み立てると、このようになる。実はポリプロピレン素材は接着剤が効かず、両面テープで貼ってもしばらくすると剥がれてきてしまう。そこで今回は各パーツをネジ止めしてみた。一応はしっかり組み立てられたが、ポリプロピレンは軟質素材のため、ネジ止めはけっこう難しく、そのためちょっと不規則になってしまった。
裏から見たところだが、中にストロボの発光部を仕込み、穴から配線を出している。
ストロボ本体にさらなる改造を加えたのだが、まず側面にストロボブラケットを素材にした「可動アーム」を取り付けた。このアームを固定するねじ穴が、実はストロボの電池ボックスに干渉し、電池が入らなくなったのである。そこで市販の単3電池ボックスを、ストロボ本体に外部に取り付け、内部の電極に接続した。もともと単4電池使用のストロボだったが、電池容量が単3にアップし実用性も増したのである。
可動アームにライトボックスをネジ止めすると、「可動式マクロツインストロボ」が完成する。
Macro Quinon 55mm F1.9を装着したPEN-Fに「可動式マクロツインストロボ」を装着すると、このようになる。これはレンズを繰り出さない無限遠の状態。
レンズを最大限に繰り出したところだが、それに合わせて可動アームを調整して、レンズ先端に発光部を移動させることができる。これによってレンズ前約4cmの被写体に、柔らかい光をまんべんなく照射することができる。大仰なシステムのように見えるが、ストロボシステムそのものは軽量にできている。
背面から見たところだが、サンパックPF20XDはダイヤル操作で発光量をマニュアルで調節することができる。カメラの露出モードもマニュアルに設定し、こうすることで安定した思い通りの露出で撮影できるのである。
テスト撮影
上記のように、やっとの思いでMacro Quinon 55mm F1.9を実用的に使えるシステムが完成したのだが、そうなるとこのレンズがどれほど高性能なのか試してみたくなる。そこで、オリンパスが誇る最新のマクロレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro」と簡単な比較撮影を行ってみることにした。
まず外観の比較だが、ずんぐりしたMacro Quinon 55mm F1.9に対し、M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroは細身だが、両者の見た目のボリュームはそう大差が無いと言える。しかし重量はMacro Quinon 55mm F1.9が500gに対し、M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroは185gと半分以下である。
さらにM.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroはインナーフォーカスを採用し、等倍撮影時においても鏡筒が伸びることが無く、十分なワーキングディスタンスが確保できる。使い勝手で言えば、最新のAFレンズの方が遥かに上だと言える
被写体は「ネジバナ」という蘭の一種を選び、それぞれのレンズで1/2倍と、1倍(等倍)で比較撮影をしてみた。
もちろん今回改造した「可動式マクロツインストロボ」を発光させているが、さらに植物の透明感を出すために、オリンパスの「エレクトロニック フラッシュFL-600R」を斜め上からスレーブ発光させている。
絞りはどちらのレンズもF8に設定している。本当は絞り開放から1段ずつ変えて比較撮影してみたかったのだが、今回ひさしぶりにMacro Quinon 55mm F1.9を使ってみたところ、あいにく自動絞り機構が不調で、やむを得ず絞りF8固定で使う事にしたのである。
◇ ◇
以下、左にMacro Quinon 55mm F1.9の写真を、右にM.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroの写真をレイアウトしている。
さて倍率1/2倍(ライカ判換算等倍)での比較である。左のMacro Quinon 55mm F1.9に比べて、右の「M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro」の方がコントラストが高く、黒の締まりが良いのがわかる。
被写界深度はMacro Quinon 55mm F1.9の方が若干浅く、背景ボケもより大きいが、これは単純な「全群繰り出し式フォーカス」と、最新鋭の複雑な「インナーフォーカス」との違いによるものだ。そしてマクロレンズとして肝心のシャープネスだが、どちらのレンズもほぼ同等なのである。Macro Quinon 55mm F1.9の性能の高さに、あらためて驚いてしまった。
次に等倍(ライカ判換算2倍)での比較だが、やはりM.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroの方がコントラストが若干高いものの、どちらもマクロレンズとして非常にシャープな描写をしているのである。
最後にMacro Quinon 55mm F1.9ならではの1.4倍(ライカ判換算2.8倍)での撮影だが、等倍時よりもシャープネスが若干落ちているように思える。やはりフローティング機能を装備していないせいだろうが、少なくとも等倍までは最新レンズに引けを取らないシャープな描写をすることがわかったのである。
なお今回は撮影結果を掲載できなかったが、絞りF2.8での撮影ではMacro Quinon 55mm F1.9がソフトな描写なのに対し、M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroはかなりシャープで、この点では最新レンズの方が優れていることを、付け加えておきたい
実写作品とカメラの使用感
Macro Quinon 55mm F1.9の描写性能の高さがあらためて確認できたところで、藤沢市内の自宅近くを散策しながら、花や虫を撮影してみることにした。
レンズの絞りはF8に固定し、PEN-Fの露出モードはマニュアルに設定、WBも基本的に太陽光に固定した。また「可動式マクロツインストロボ」を発光させ、必要に応じてFL-600Rをスレーブ発光させている。
PEN-Fそのものの使い勝手はかなり良く、基本的な操作で迷うところはないだろう。ファインダーもEVF、背面モニター共に高精細で、MFレンズを装着してのピント合わせが非常にしやすい。今回はレンズの絞りをF8固定で使ったが、マクロ域では被写界深度が浅く、ピントの山が確認しやすいため、拡大モードをほとんど使わずにピント合わせができた。
自作した「可動式マクロツインフラッシュ」は、当初の目論みどおりワーキングディスタンス約4cmの1.4倍撮影時においても、被写体を柔らかな光で照射することができる。ただし、レンズの繰り出しと、フラッシュの可動アームは連動しないので、まず撮影倍率を決めて、それに合わせて可動アームを調整し、発光部をレンズ先端に固定した。この操作がちょっと面倒で、その点でこのシステムは改良の余地がある。
もちろん最新のM.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroを使えば、遥かに簡単で確実なマクロ撮影は可能だ。しかしかつて世界をリードしたドイツの光学技術者が、使い勝手を無視してまでハイスペックを追求したレンズを、デジタル時代に相応しくアレンジして使いこなすのも、また別の意味で楽しいのである。
◇ ◇
池の水面に咲いていた、オオカナダモの花。1/1.4倍(ライカ判換算1.4倍)で撮影したが、花粉はもちろん花びらを構成する細胞の一粒一粒までが見える。オオカナダモは南アメリカ原産で、日本では1940年に野生化が確認されて以後、棲息範囲を拡大したとされている。
土手にたくさん咲いていたハルシャギク。撮影距離40cmにて撮影。実にシャープな描写で、ボケも自然に見える。花の名前の「ハルシャ」はペルシャの意味だが、実際の原産地は北アメリカで、明治期に園芸品として輸入されたものが、雑草化したとされている。
同じハルシャギクの花の中心部を、等倍(ライカ判換算2倍)にて拡大撮影してみた。ハルシャギルはキク科の植物で、1つの花にたくさんの小花が集合して咲いている。その繊細な構造を、このレンズは実にシャープに描写している。
ヒルガオツキミソウの雄しべを等倍(ライカ判換算2倍)にて撮影。拡大して見ると、この花に特有の金平糖のような形の花粉を確認することができる。
ヒルザキツキミソウの花全体を撮影距離30cmにて撮影。これも北米原産の帰化植物で、道ばたや空き地でもよく見掛ける。小雨が降って花びらに水滴が付いたので、その雰囲気で撮影した。背景の光ボケが五角形に写っているが、これはレンズの絞りの形である。このレンズは自動絞りを作動させるため、絞り羽根を5枚と少なくしているのである。
アガパンサスは南アフリカ原産の帰化植物だが、分類方法によってヒガンバナ科、ユリ科、アガパンサス科という具合にまちまちのようで、なかなか難しい。撮影距離60cmだが、拡大すると花粉や花びらの細胞の粒立ちまでもが確認できる。
アガパンサスの雄しべを等倍(ライカ判換算2倍)にて撮影したが、花粉の米粒のような形状までもが確認できる。
ここからは昆虫なのだが、まずは葉っぱに止まって休んでいたベニシジミ。拡大すると、超の羽の模様がピクセル(鱗粉)によって描かれているのがよくわかる。1/2倍(ライカ判換算等倍)にて撮影。
ツバメシジミは一見、良くいるヤマトシジミに似ているが、翅に尻尾が生え、オレンジのアクセントも入り、ちょっとゴージャスな仕様になっている。1/2倍(ライカ判換算等倍)にて撮影。
ツバメシジミが大人しく止まっていたので、等倍(ライカ判換算2倍)で顔面付近を拡大してみた。しかしチョウはじっとしているようでも、微妙に姿勢を変えたりするので、ピント合わせはなかなか難しい。
ヒャクニチソウの蜜を吸うモンキチョウ。シジミチョウより大きなチョウなので、撮影距離30cmにて撮影。ちなみに今回の撮影は、どれもまず撮影距離(倍率)を決めてピントリングを固定したまま、カメラを前後させてピント合わせをした。
同じモンキチョウを等倍(ライカ判換算2倍)にて撮影。チョウの複眼やストロー上に延びた口吻など、機能的な部分に美味くピントを合わせることができた。
次からはチョウ以外の虫だが、まずはツチイナゴの幼虫で、いかにも「子供」といった感じでカワイイ。等倍(ライカ判換算2倍)で撮影したところ、F8に絞っても被写界深度は浅くなったが、セオリーどおり「目」にピントを合わせてみた。
ツユムシはもう成虫になっていたので、撮影距離40cmで全身像を捉えた。しかしカメラを近づけるとゆっくり逃げようとするので、少し追いかけて何枚か撮影し、ベストのものをセレクトした。
エノキの葉を食べるエノキハムシが、葉っぱの裏に止まっていた。半透明な翅がきれいな甲虫である。等倍(ライカ判換算2倍)にて撮影。
クズの葉っぱの裏で交尾していた、メダカナガカメムシ。2mm程度という極小サイズのカメムシで、最大の1.4倍(ライカ判換算2.8倍)にて撮影した。
自分の手に止まったヤブカ(ヒトスジシマカ)を1.4倍(ライカ判換算2.8倍)にて撮影。この倍率になるとピント合わせはかなりシビアになるが、血を吸っている間は大人しくしているので、じっくり撮影できる。
アリマキ(アブラムシ)のコロニーにいたアミメアリ。二匹が会話しているように見えるが、働きアリが互いに何らかのコミュニケーションを行っているのは確かである。等倍(ライカ判換算2倍)にて撮影。
NHKのクレイアニメ「ニャッキ!」のモデルだと言われているのがハバチの幼虫で、つぶらな目に特徴がある。これはハグロハバチの幼虫で、イタドリの葉をもりもり食べている。こう見えてチョウやガではなく、原始的なハチの幼虫である点も面白い。
葉っぱの裏に隠れて獲物の虫が来るのを待っているハナグモ。特徴的な8つの単眼の他、体表のディテールまで分かって面白い。
ここからは参考までに、マクロではない風景写真をご覧に入れようと思う。
上記の花や虫を撮影していた田んぼで、天気はあいにくの曇り空だが、画面中心から隅々までシャープに写っていて、これにも驚いてしまった。Macro Quinon 55mm F1.9が採用したレンズ構成「ダブルガウスタイプ」は撮影倍率の変動に強いとされており、そのことがあらためて実証されたのである。ちなみに以前に連載で取りあげたテッサータイプのマクロレンズ「Macro Kilae 40mm F2.8」は遠景描写は芳しくなく、対照的な結果となった。
晴天の住宅街で撮影してみたが、こちらもシャープで、しかも歪曲もなく直線がまっすぐに写っていて気持ちが良い。OLYMPUS PEN-Fに装着すると「ライカ判換算110mm相当」の中望遠レンズとなり、その圧縮効果も楽しめる。
夕方の住宅街を逆光で撮ったところ、かなりフレアが出た。やはり高性能とは言え50年以上も前の設計のレンズであり、最近のレンズとは異なっている。ダブルガウスタイプのレンズはシャープな反面逆光に弱く、コーティング技術の発達と共に、広く採用されるようになったとされている。
