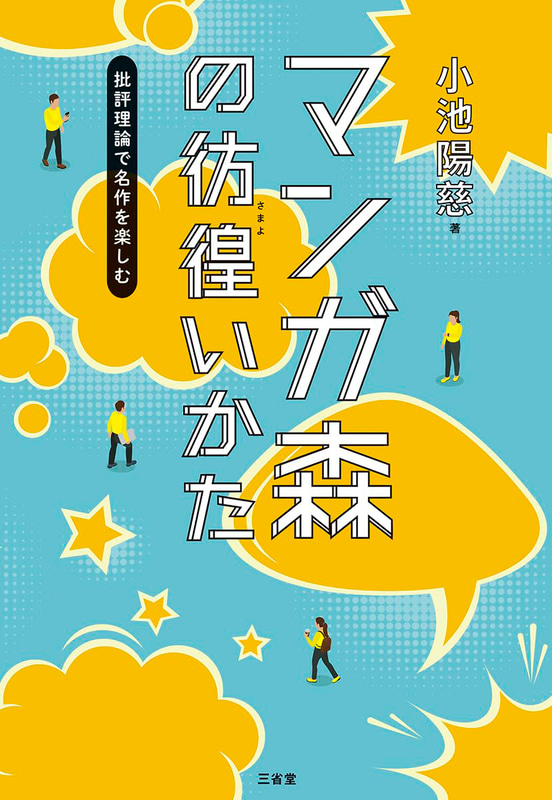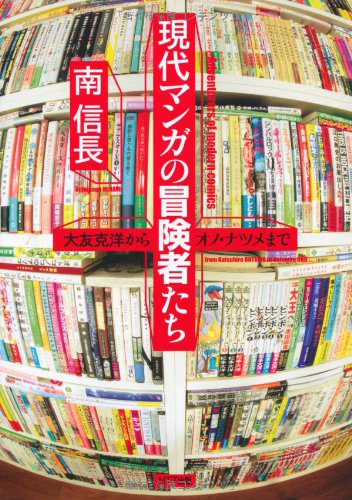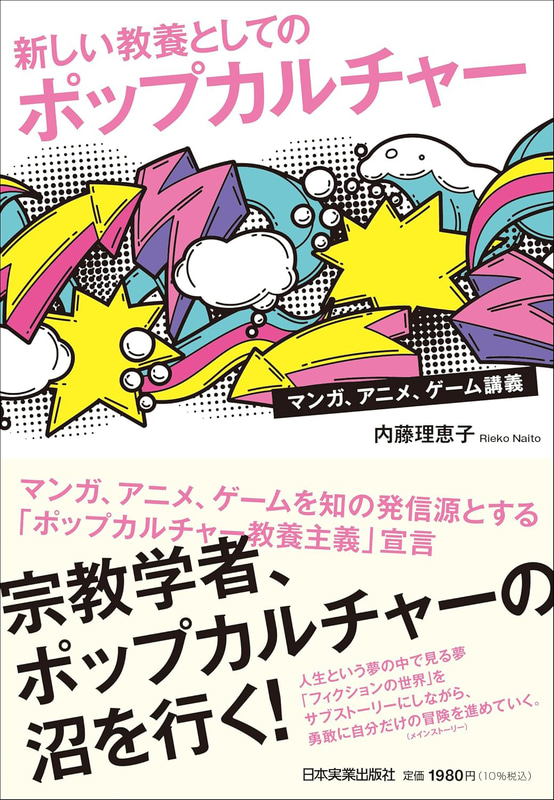写真を巡る、今日の読書
第96回:「マンガ論」から深める教養――写真と異なる視点を
2025年10月29日 07:00
写真家 大和田良が、写真にまつわる書籍を紹介する本連載。写真集、小説、エッセイ、写真論から、一見写真と関係が無さそうな雑学系まで、隔週で3冊ずつピックアップします。
写真と同じくらいの歴史の中で
残暑を感じるような日もようやく少なくなり、夜はずいぶんと過ごしやすくなったように思います。この時期になると、学生たちは年間の自主制作課題へ取り組む時間も増え、ステートメントやレポート作成のために様々な芸術論や写真論を読むことも多くなります。
本連載でも、写真に関する理論書は様々紹介してきましたが、時には他の分野のメディア論や芸術論に触れてみると、新たな視点が得られるのではないかと思います。
今日はその中から、「マンガ論」に焦点を当てていくつか紹介したいと思います。マンガの歴史は、さかのぼれば葛飾北斎の「北斎漫画」など江戸時代から続いていますが、いわゆる今の「マンガ」というのはだいたい明治時代から盛んに描かれるようになったようです。そう考えると大体写真と同じくらいの歴史の中で、その技術や方法論、メディア論が発達してきたものと考えられそうです。
時代の特徴を追うのも面白そうなのですが、まずは、現代のマンガについて取り上げられている書籍に目を向けてみたいと思います。
『マンガ森の彷徨いかた』小池陽慈 著(三省堂/2024年)
1冊目は、『マンガ森の彷徨いかた 批評理論で名作を楽しむ』。本書は、マンガ作品の読み解きを通じて、著者小池陽慈の専門領域である「批評理論」、「文学理論」の基礎的な考え方を学ぶことができる1冊です。
予備校で現代文の講師も務める著者の文章は非常にわかりやすく、要点を押さえた講義風の解説となっています。また、取り上げられる内容としては、「シニフィエとシニフィアン」や「デノテーションとコノテーション」といったロラン・バルトの写真論などでも見かける用語の解説もあり、写真からの解説とはまた違う視座での用語解説はとても新鮮で興味深く読むことができました。
登場するマンガには、松本大洋の『Sunny』や、山田鐘人/アベツカサ『葬送のフリーレン』、山下和美『ランド』など様々な作品があります。
◇
『現代マンガの冒険者たち』南信長 著(NTT出版/2008年)
2冊目は、『現代マンガの冒険者たち』。井上雄彦や鳥山明、大友克洋、浦沢直樹などの作品がなぜ「すごい」のかが良くわかる「現代マンガ進化論」です。
それぞれの作家の立ち位置や影響を図説しつつ、作家の個性を表現方法や時代的背景から解説しています。対象としている漫画家も、現代を代表する作家が集められているため、自分が単純に「面白い」と感じながら読んでいたその奥に、作家としてのどんなすごみがあったのかを改めて知ることができます。
なによりもところどころで掲載される分布図やチャート、系譜図が非常にわかりやすく、その図で漫画家同士のつながりや影響を見ているだけで多くの発見があります。
◇
『新しい教養としてのポップカルチャー』内藤理恵子 著(日本実業出版社/2022年)
最後は、『新しい教養としてのポップカルチャー マンガ、アニメ、ゲーム講義』です。マンガ、アニメ、ゲームの3つのメディアを通してポップカルチャーとはなにか、また新しい教養とはなにかを論じる評論書です。
『ドラゴンボール』や『スラムダンク』の自己啓発性、『スライム倒して300年』をはじめとする転生モノの来世観、ゲームにおける「死」の扱い方、など非常に興味深い考察が多く見られます。
特にマンガの項では、先に挙げた2冊のなかでの取り上げ方などと比べながら読んでみると大変面白いのではないかと思います。