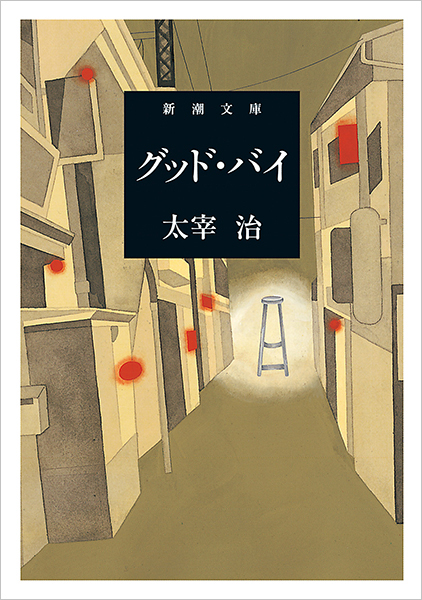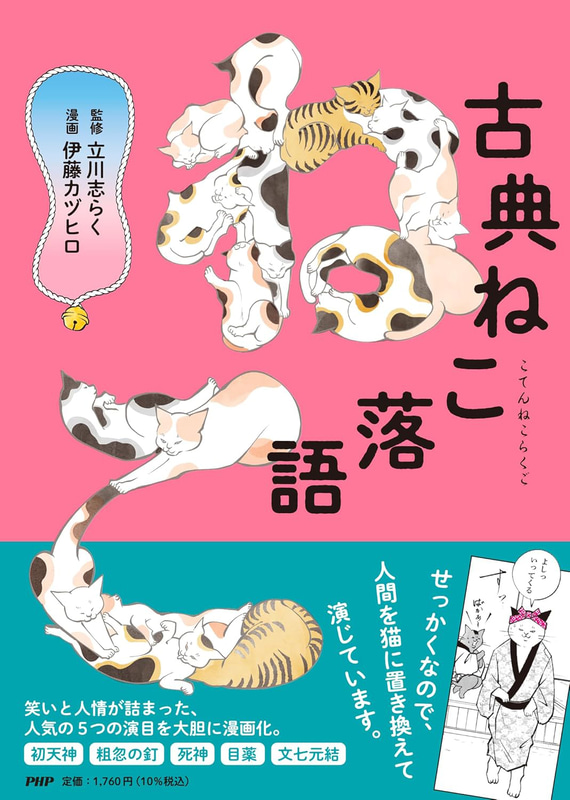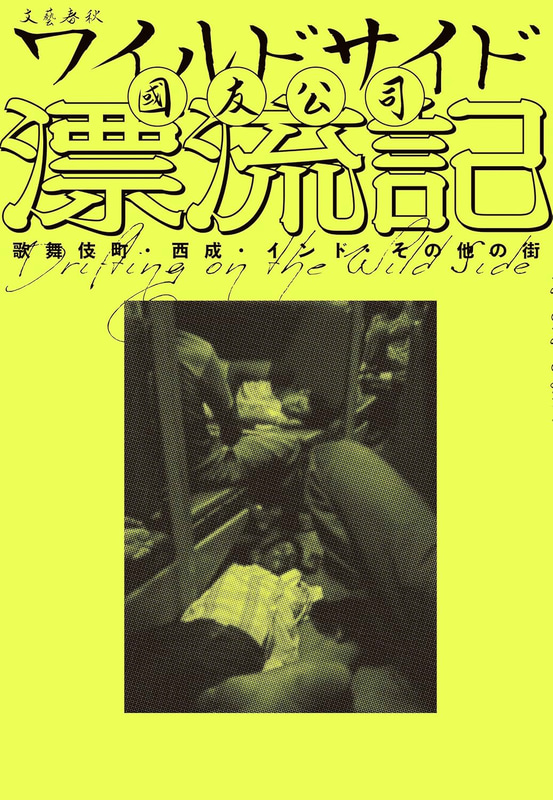写真を巡る、今日の読書
第93回:旅先で「旅の物語」を読む―出会った人々と結びつく、その土地の記憶
2025年9月17日 07:00
写真家 大和田良が、写真にまつわる書籍を紹介する本連載。写真集、小説、エッセイ、写真論から、一見写真と関係が無さそうな雑学系まで、隔週で3冊ずつピックアップします。
スウェーデンの夏
先日まで約2週間、スウェーデンのストックホルムに滞在していました。現地の写真学校で講演やワークショップを行ったほか、ゼミの学生を引率して研修も実施し、充実した海外出張となりました。
何よりも驚いたのは、東京とは比較にならない涼しさです。日中でも気温は15℃程度、夜は10℃を下回り、日本の晩秋のような気候でした。朝は6時頃には陽が上り、夜は8時過ぎまで明るいため、1日中スナップ撮影に歩き回るのには最適の気候だったと思います。
ちなみに、昨年11月末に訪れた際は雪が降り、気温はおよそ-5℃まで下がっていたため、今回とはまったく異なる景色でした。ストックホルムは歴史的な街並みが美しく、アートギャラリーや美術館も豊富で、写真やアート好きにはぜひ訪れてほしい都市のひとつです。
出張や旅行の際の読書についてですが、私は軽量なソフトカバーの本を3冊ほど持参するようにしています。ジャンルはできるだけ異なるものを選び、漫画などを組み合わせることもあります。そこで今回は、先日の海外研修に携えた本をいくつかご紹介したいと思います。
『グッド・バイ』太宰治 著(新潮文庫/2008年)
1冊目は『グッド・バイ』。太宰治の後期短編を収めた1冊です。太宰の作品はこれまで、さまざまな時期や場所で繰り返し読み返してきました。ロサンゼルスやメルボルン、ローザンヌ、そして日本でも、同じ物語を何度も開いていますが、不思議なことに、そのたびに印象や受け止め方が異なります。
たとえば、本書に収められている随筆的な「苦悩の年鑑」も、ユーモアと哀愁が入り混じる「メリイクリスマス」も、読むたびに少しずつ違ったイメージが立ち上がり、読後感さえ変わってゆくのです。
今回は太宰を選びましたが、ほかには夏目漱石や川端康成、寺田寅彦などの短編集や随筆集を携えることが多いように思います。
◇
『古典ねこ落語』立川志らく 監修(PHP研究所/2024年)
2冊目は『古典ねこ落語』。立川志らくが監修しており、「初天神」や「死神」など、十八番ともいえる噺が収められています。読んでいると、高座に響く声まで聞こえてくるような気がします。
すべての登場人物が猫として描かれた漫画作品なのですが、そのユーモラスな姿が、人間以上に身近で親しみ深く感じられます。落語ゆえに繰り返し楽しめる面白さがあり、私自身、機内などの移動時間に落語を聴くことが多いため、今回の旅にぴったりの1冊となりました。
◇
『ワイルドサイド漂流記 歌舞伎町・西成・インド・その他の街』國友公司 著(文藝春秋/2025年)
3冊目は『ワイルドサイド漂流記 歌舞伎町・西成・インド・その他の街』。旅に出るときは必ず1冊、旅や冒険に関する本を選ぶことにしています。旅先で「旅の物語」を読むことで、日常とは異なる不思議な趣きが立ち上がるからです。
本書はさまざまな土地のドヤ街に入り込み、そこで出会った人々を取材したエッセイ。神に祈るために金を要求する老婆、廃墟のラブホテルを拠点にする男性、筋トレにしつこく誘うモンゴル人青年など、強烈な個性をもった人物たちが生き生きと記録されています。
「街の記憶とは、そこで過ごした人との思い出に結びついている」という一節に触れ、私自身も、これまで出会った人々とその土地の記憶が分かちがたく結びついていることに改めて気づきました。
ストックホルムの涼しい夜に、歌舞伎町や西成の一場面を読むと、日本という国までの距離がより強く感じられると同時に、私の知る歌舞伎町とは異なるもう1つの街の景色が浮かび上がってくるようです。