切り貼りデジカメ実験室
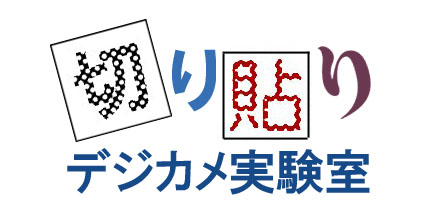
APSフィルムカメラ専用「IXニッコール」をフルサイズ機に装着
(2012/12/21 17:05)
APSフィルムカメラ用レンズをフルサイズデジタル一眼レフに装着
現在のデジタル一眼レフの標準とも言えるフォーマットは「APS-C」サイズだが、この語源は読者の皆さんならご存じだろう。APSフィルムCタイプ(画面サイズ23.4×16.7mm)の呼び名を継承しているのである。
APSは正式名称アドバンストフォトシステム (Advanced Photo System) で、35mmフィルムに変わる新規格として1996年4月に販売が開始された。APSフィルムはカメラへの装填が簡単なカセット式で、撮影データを磁気によって書き込むなどの利点があるとされていた。
しかし35mmフィルムより画面が小さい分画質が劣り、現像済みのカセットも意外に保存が面倒だったりして、けっきょく主流になれず、ついに2012年5月にAPSフィルムの販売が終了してしまった。
それでも一時期は各社から様々なAPSフィルム用カメラが発売され、ニコン、キヤノン、ミノルタからはレンズ交換可能な一眼レフも発売されていた。
このうちニコンのAPSフィルム一眼レフはプロネア(PRONEA)シリーズとして発売されていた。ニコンFマウントを採用し、35mm一眼レフ用レンズも可能で、APS専用レンズ「IXニッコール」も用意されていた。
IXニッコールはFマウントを採用しているものの、レンズ後部が突出しているため35mm一眼レフには装着できない。しかしそのぶん小型軽量を実現していたのだ。
このうち「IX Nikkor 30-60mm F4-5.6」はズームレンズでありながら単焦点レンズより小さく、同じく小型軽量のAPSフィルム一眼レフ「プロネアS」とセット販売されていた。
ぼくはこのIX Nikkor 30-60mm F4-5.6を、確か10年くらい前に購入したのだが、その当時も投げ売りで3,000円くらいだったと思う。実はぼくはプロネアは持ってなかったのだが、このレンズを改造し35mm一眼レフに装着する“実験”を行なったのだった。
その結果は意外にも広角端30mmからケラレが無く、普通に35mm用ズームレンズとして使えてしまうのだった。もちろんピントはマニュアルで、絞りも最小値に固定されてしまうことから実用には厳しい。
しかし、かつてのこの実験をデジタルで試してみたら……とふと思い出したのである。というわけで、FXフォーマット機であるニコン「D700」を素材に、当時の実験を再現しつつIX Nikkor 30-60mm F4-5.6のデジタルでの性能を検証してみることにした。
―注意―- この記事を読んで行なった行為によって、生じた損害はデジカメWatch編集部、糸崎公朗および、メーカー、購入店もその責を負いません。
- デジカメWatch編集部および糸崎公朗は、この記事についての個別のご質問・お問い合わせにお答えすることはできません。
テスト撮影
テスト用の被写体は歪曲を含めてテストができる「金網チャート」だが、ぼくが国分寺市から藤沢市に転居したため、これまでとは場所が異なっている。ピントはいずれもMFで遠景の被写体に合わせている。
今回の改造レンズは絞り固定なので、各焦点距離の違いのみのテスト撮影を行った。露出はマニュアルモードでシャッター速度で微調整している。参考までにAF-S NIKKOR 24-70mm F2.8 G EDでの比較もしてみたが、こちらも絞り固定でシャッター速度も固定で撮影している。
本来APSフィルム専用であるIX Nikkor 30-60mm F4-5.6だが、ライカ判フルサイズでもけられなく使用できることに驚いてしまう。もちろん広角30mm域で四隅の画質が崩れたり、歪曲収差も大きいなどの欠点もある。しかし総合的に描写を判断するとAF-S NIKKOR 24-70mm F2.8 G EDと比較して顕著に劣るとは思えない。
もちろん、絞り開放で比較すれば描写の差はハッキリ出るだろうが、仕様を考えればかなり健闘していると言える。30-60mmという画角は常用レンズとして不足無く、このような超小型軽量ズームがデジタルのFXフォーマット用にも発売されると面白いかも知れない。
・IX Nikkor 30-60mm F4-5.6
・AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8 G ED
使用感と作品写真
実は今回使用したD700は、ぼくにとっては初めて使う“ライカ判フルサイズ”のデジタルカメラなのだった。本当は最新機種の「D600」か「D800」をメーカーからお借りしたかったのだが、企画の趣旨から編集部にある一世代前のD700をお借りしたのだ。
確認するとD700はもう4年前の2008年発売で、時の流れが速いのに驚いてしまう。しかしあらためて手に取ったD700は非常に質感が高く、高機能で操作もしやすく、古さというのはほとんど感じられない。D一桁シリーズに対する普及機とは言え、ニコンの力の入れようが分かるカメラで“良い物は良い”と言った印象だ。
当たり前だがD700は改造したIX Nikkor 30-60mm F4-5.6を装着すると30-60mm相当の画角で使える。日頃フォーサーズやAPS-Cサイズのデジカメを使って“換算○○mm”という計算に馴染んでしまっているため、初めのうち「あれ?」と戸惑ってしまうのが自分でもおかしかった。
この改造レンズは当然マニュアルでピント合わせを行なう。暗いズームのせいか、D700のスクリーンでピント合わせするのは至難の技だが、ふとフォーカスエイドが使えることに気付き、途中からは専らこれに頼っていた。露出もマニュアルで合わせたが、今回の改造レンズは絞り値固定なので、シャッター速度とISO感度で調整した。
ズームは30mmから60mmまでを駆使しながら撮影したが、もちろんExif情報には記録されない。だから撮影するごとに焦点距離をiPhoneでメモしていたのだが、けっきょくどれがどれだか分からなくなってしまった(笑)。まぁ、フィルムカメラの感覚でおおらかに見てもらえればと思う。
「反-反写真」から「写真」へ
今回の作品も「反-反写真」のシリーズで、気分を変えてカラーで撮影してみた。しかし前々回の記事『スライドビューワーで作る「コンツールファインダー」』で告白したとおり、自分の中でこのコンセプトは行き詰まっている。
そもそも「反-反写真」と言ったような、他人とは違うヒネクレた態度で写真に臨んでるうちは、まだ未知の世界が広がっていて楽しいのである。しかし、子供がいつまでも反抗期でいられないのと同じように、反抗だけのアートは長続きしない。
だからぼくもそろそろ「反-反写真」などと気取っている場合ではなく、いよいよ「写真」そのものと対面しなければならないところに追い詰められている。
あらためて気付いたのは、自分の“写真”に対する絶対的な知識不足である。ぼくはカメラが好きなのでカメラの歴史はだいたい頭に入っているのだが、実のところこれまで写真にはあまり興味が無く(だから「反写真」の方向に行ったのだが)、“写真の歴史”もほとんど知らないのだ。
そもそもたいていの写真家は写真学校や美大の写真学科で学んでおり、これまでどんな写真家によってどのような写真家が撮られてきたのか、その歴史をそれなりに把握している。写真の歴史を学べばそれが“基準”となって、自分の写真を確固として打ち立てることができるだろう。
そしてまさに、ぼく自身はその基準を持たないことに、あらためて気付いたのである。
もちろんぼくも自分なりの基準を持っており、そのお陰で「フォトモ」や「ツギラマ」など独自の写真表現が追求できたと言えるだろう(前回紹介した「ひも宇宙」写真もその延長にある)。しかし基準は常に強化されなければならないし、また複数の基準を縒り合わせた方が表現に幅が出るというものだ。
ともかく今の自分は“写真”の難しさがだんだんわかってきて、そして“写真”というものがどんどんわからなくなって来ている状態だ。まぁ、実のところカメラ改造記事の“作例”を撮るだけならそんなに悩むことはないのかも知れないが、アーティストはある意味悩むのが仕事だし、悩むのもぼくの“芸”だと思って今後の連載も楽しんでいただければと思う(笑)。
