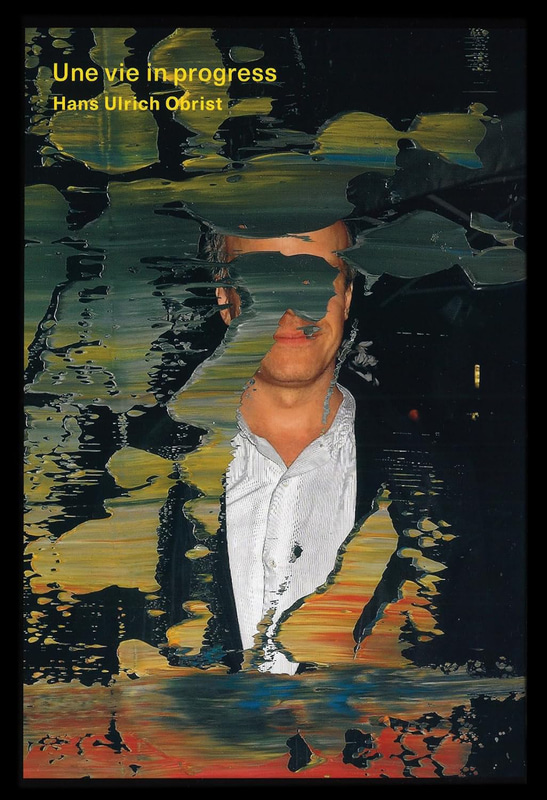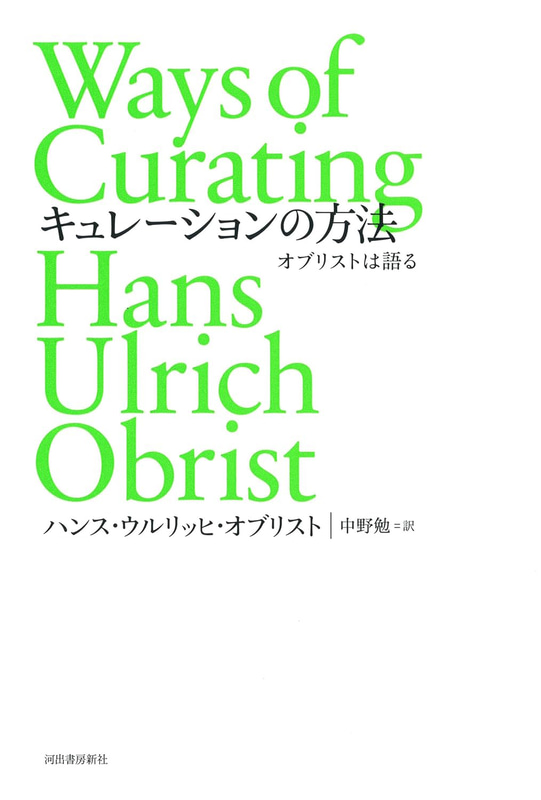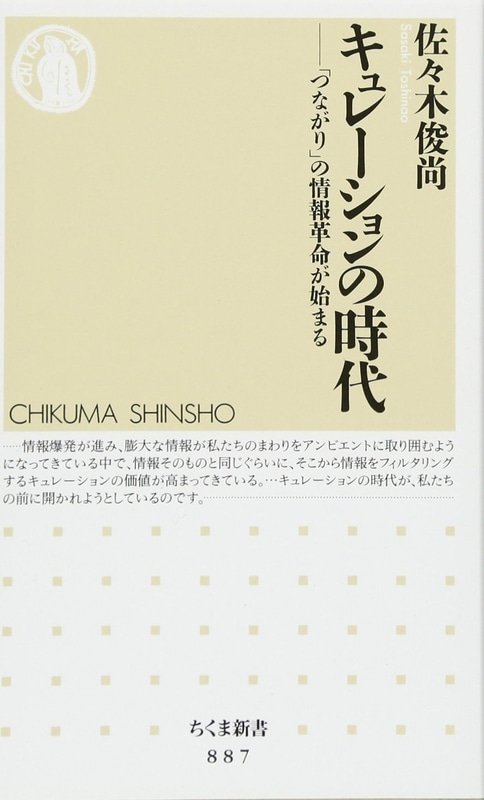写真を巡る、今日の読書
第98回:創造的な場を生みだす方法論――「キュレーション」の役割を考える
2025年11月26日 07:00
写真家 大和田良が、写真にまつわる書籍を紹介する本連載。写真集、小説、エッセイ、写真論から、一見写真と関係が無さそうな雑学系まで、隔週で3冊ずつピックアップします。
「キュレーション」の普及
「キュレーション」という言葉が社会に定着してずいぶん経つように思います。もともとは、美術館や博物館で展示の企画・選定・運営を担う「キュレーター(学芸員)」に由来する言葉です。そのため、美術や芸術に詳しい方々には以前から馴染みのある用語でしたが、近年は「キュレーションサイト」などの用語の普及によって一般的にも広まったと考えられます。
キュレーションサイトとは、いわゆる「まとめサイト」のことで、たとえば「NAVERまとめ」(2020年にサービス終了)のように誰でもまとめ記事を作成・公開できるものや、「グノシー」「NewsPicks」のように運営者によって情報がまとめられているものがあります。さらに、その運用方法も多様で、実際に人がまとめる場合もあれば、AIや独自アルゴリズムで情報を抽出するものまで存在します。
最近では、芸術・美術・メディア系大学でも情報発信に関わるキュレーション教育がより一層重視されるようになっています。個人的には「キュレーション」と聞くと、真っ先にハンス・ウルリッヒ・オブリストの名前が思い浮かびます。現代アートのキュレーションそのものや展覧会の歴史に大きな影響を与えてきた、長く第一線で活躍するキュレーター/ライターで、学生時代、雑誌のレビュー記事でオブリストが企画した展覧会を知り、インタビュー集や評論集も積極的に読むようにしていました。
『未完の人生 ハンス・ウルリッヒ・オブリストは語る』ハンス・ウルリッヒ・オブリスト 著(草思社/2025年)
本日最初に紹介する『未完の人生 ハンス・ウルリッヒ・オブリストは語る』は、オブリスト本人が自身の半生やキャリアを語る自伝的な作品です。
幼少期の体験も興味深いですが、特に高校生時代のギャラリー巡りや人々との交流についての記述は非常に示唆に富んでいます。私自身や周囲には、その年頃から現代アートに夢中になっている生徒はいませんでしたので、本書を読みながら、オブリストの育った環境や、基礎的な教養・好奇心の高さに驚きました。
作中では、ゲルハルト・リヒターやクリスチャン・ボルタンスキー、ルイーズ・ブルジョワといった著名な現代アートの巨匠たちから受けた影響や、オブリストがどのように柔軟な思考力や創造的なコラボレーション力を育んだかが生き生きと描かれています。
◇
『キュレーションの方法』ハンス・ウルリッヒ・オブリスト 著(河出書房新社/2018年)
次に紹介する『キュレーションの方法』は、オブリストの思考が実際のキュレーション実践としてどう形になっていくかに焦点を当てています。
オブリストは、キュレーターの役割を「交差点を作る存在」と捉え、異なる文化や視点、分野を横断して新たな対話や実験の場を生み出す方法を語っています。また、「Curare(面倒を見る、~を受け持つ)」というラテン語に由来するキュレーターの語源が、現代のキュレーターの「育てる」「剪定する」「発展を手助けする」といった役割と重なることにも触れられており、仕事内容やキュレーションの意義についても詳述しています。
もし若い頃にこの本に出会っていれば、新たな進路の1つとして意識していたかもしれません。美術・芸術分野に限らず、創造的な場を生みだす方法論に興味のある読者にもおすすめです。
◇
『キュレーションの時代「つながり」の情報革命が始まる』佐々木俊尚 著(筑摩書房/2011年)
最後に紹介するのは、オブリストとは少し離れますが、メディア論や情報論だけでなく、政治・経済・ライフスタイルの分野でも著作の多い佐々木俊尚による『キュレーションの時代 「つながり」の情報革命が始まる』です。
本書は、美術・芸術分野におけるキュレーションではなく、現代ネットメディアの膨大な情報をどのように選別・収集・共有するかに焦点を当てています。従来の大量消費型情報社会から、個々人が自分の価値観で情報や人とのつながりを構築する時代に移行する現在において、新しいコミュニティと個人の主体性がどう機能するかが論じられています。
2011年発行と、15年近く経過した新書ながら、この視点はいまも十分に有効だと感じます。現代のAI時代においては、個々人のキュレーション能力が一層進化し、その発信と共有から生まれるコミュニティは、メディアのあり方そのものを変え続けるはずです。むしろ、2011年当時以上に、2025年現在はよりダイナミックに情報社会の輪郭が変化しているといえるでしょう。